中小企業の経営者・人事ご担当者からよくいただくご質問のひとつが「就業規則の作成義務」です。本記事では、まず最初に結論をお伝えし、その後に法的根拠・実務ポイント・リスクについて解説します。熊本をはじめ全国対応の岩根事務所が、経営者の視点でわかりやすく整理しました。
Q:就業規則は何人以上で作成義務がありますか?
A:結論
結論:常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。10人未満の場合は義務ではありませんが、労使トラブル防止のため整備が強く推奨されます。
背景と法的な位置づけ
- 根拠法令:労働基準法 第89条
- 対象人数:常時10人以上の労働者(正社員・契約社員・パート・アルバイトも含む)
- 届出先:所轄の労働基準監督署
実務での運用ポイント
- 社員数のカウント:役員を除き、雇用契約を結んでいる全労働者を人数に含める。
- 作成内容:労働時間、賃金、休暇、服務規律、懲戒、退職などを必ず記載。
- 手続き:労使協議(意見聴取)→労働基準監督署に届出。
- 周知方法:社内掲示、イントラネット、配布など。
やりがちなNG・リスク
- 社員数の数え方を誤り、義務を見落とす。
- 厚労省のモデル就業規則をそのまま流用し、自社に合わない規定になる。
- 従業員への周知不足で効力を失う。
よくあるケース
- パート・アルバイトも人数に含まれますか?
- はい。雇用契約を結んでいる労働者はすべてカウントします。
- 10人を下回ったら届出は不要ですか?
- 義務はありませんが、整備しておくとトラブル防止になります。
- すでに届出した就業規則を変更する場合は?
- 変更時も労基署への再届出が必要です。
岩根事務所のサポート
岩根事務所では、中小企業の実情に合わせた就業規則の作成・改定・届出をサポートしています。
単なる法令遵守にとどまらず、採用・定着や労使関係の安定につながる規程整備をご提案しています。
関連FAQ
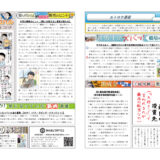 【岩根事務所通信】2025年9月号を公開しました
【岩根事務所通信】2025年9月号を公開しました
まとめ
- 就業規則は常時10人以上の労働者を使用する会社で作成義務。
- 義務がなくても整備しておくとトラブル防止に有効。
- 届出+周知まで行って初めて法的効力が発生。



